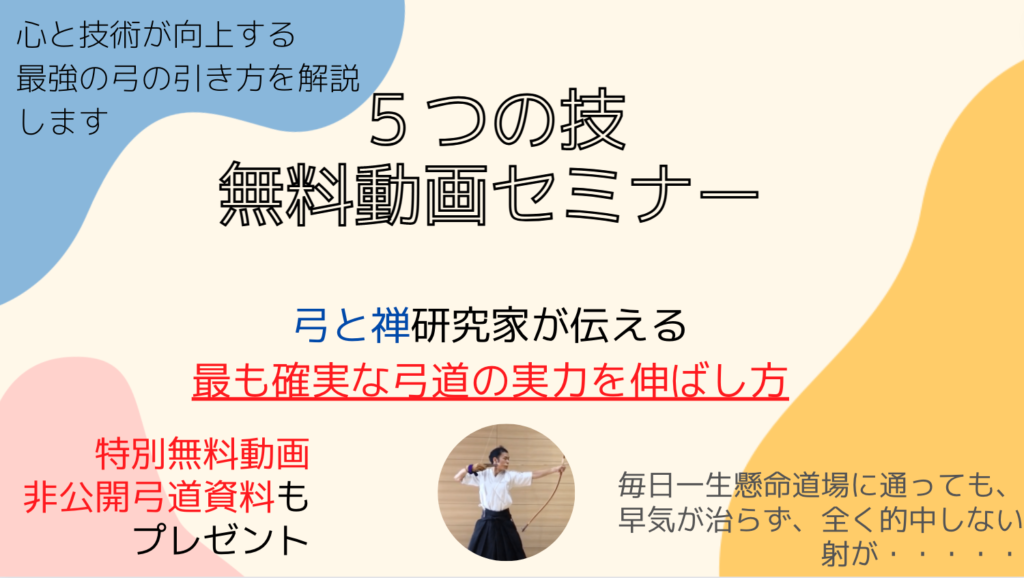日置八十八か条のまとめ
第一条足踏みを定むること
一間中墨、矢束の準、扇の準、教外別伝、沓下中墨、定時の口伝
・文章の説明
「一間中墨」とは足踏みは三尺に踏み開き、一間、六尺(約1、8メートル)の真中にいる(住む)という意味です。
重賢の定めた三尺(約0.9メートル)の広さを重政が各人各様の体格に合わせるため、その人の身長の半分とさだめました。
射手の引くべき相応の長さは、大体身長の半分のため、矢束を標準とすることとして「矢束の準」の名を用いました。
「一間中墨」は一間の中に住み、的心より中るべく墨を張り左右爪先をその上に踏むとの意であります。一間の中に住み、この6六尺の間を自分の天地として他の外界の影響を断ち切る心境を持つべきです。
「扇の準」は両足を踏み開いたときの角度の決まりです。これは軍扇の開き具合を持って標準としたので、この名があります。
しかし、「矢束の準」「扇の準」も人により一様にいきませんので、肩の上がる射手は広く踏み、落ちすぎる者は狭く踏ませます。
肥えた人は扇子の準を広く、やせたるものにはやや狭く踏ませるなど、いろいろ踏み方を応用させるのが大切です。これらの教えを「教外列伝」といい、応用であり、師たる者の責任であります。
「沓下」とは足の下、すなわち足の踏み様であって、左は爪先、右は踵(かかと)に力を入れて踏むべきであります。左の拇指に力を入れるときは急に臨んで心静まるのであり、かかるときも「中墨の準」を忘れて何もならぬとの教えであります。
「定時の口伝」に足踏みは、重要な定めであり、勝手に変えてはいけないという意味を含め、六十か条のある限り変えてはいけない、また変わらぬという意味です。
第一条の疑問点
一間中墨も、扇の準も、最後に口伝と記しています。古くの弓道の書籍でも、明確に「何メートル」「何ミリ」と決まったものは記していません。そのため、矢束の準、扇の準における「肩が上がる射手は広く踏む、落ちすぎる人は狭く踏ませる」という内容が適切かわかりません。
これは、肩が上がっている状態が良くないと判断しているからです。古くの書籍には、身体の射型、形にこだわったものは存在していないため、この教えが適切かわかりません。
他、「常定の口伝」の足踏みで勝手に変えてはいけないという説明ですが、「変わらぬ」という射は存在するのでしょうか?弓のkg数が変わってしまうと、足踏みを変えなければ、引くことは不可能です。今のところ、こうした事実を持って「足踏みが勝手にかえてはいけない」という意味がわからないでいます。
ただ、足幅が広くなると、袴が地面に擦れてしまいます。このありさまがみっともないために狭く踏ませる習わしがあります。そのため、あくまで「射型」ではなく、「社会的な背景」も交えると言葉の意味がよくわかるかもしれません。
第二条五つの胴の事
反(はん)屈(くつ)、掛(けん)、退(たい)、中(ちゅう)。中にあり、胴には名あり重政問答の事。
胴づくりには5種類あります。うしろに反るのを「反」、前にかがむのを「屈」、的に傾くのを「掛」、その反対を「退(のくともいう)」「中にあり」とは、的前および近距離の目標に対しては、そらず、かがまず、かからず、のかず、真直ぐな胴づくりを最良とします。
すべての射の修行のどうづくりの根本は、中の胴にあるとの、「胴には名あり」とは中の胴造りを中連の身ともいい、的中には、この胴造りが大事であるの意味です。
ここで、「重賢重政問答の事」でこんな話があります。「重賢重政問答の事」とは、重賢重政父子の間に行われた問答のことです。
重政は「中の胴造りを最良とするならば反屈掛退の四つの胴造は、わざわざ列挙する必要がないのではないか」とに重賢に質問しました。そしたら、重賢はこう答えました。
「この四つの胴造りは良からずといえども、それぞれ応変の胴造りとして必要なときがあります。」その具体的は話は遠距離を射るには反、動揺多いときは屈、低い時は掛、高きは退とそれぞれの適した胴造りがあると説明しました。
第二条の疑問点
上記した重賢様の回答とおり、胴体のすえ方はあらゆる種類があり、どの胴体も「適切なもの」と解釈できます。このように、解釈をすると、射を行う上で、考え方が柔軟になります。胴体のすえ方は複数適応するものがあると思います。
理由は、昔射法はあらゆる状況を想定して使われていたからです。
たとえば、現代の弓道では、弓の引き方を28メートル先を想定して解説されます。しかし、昔の射法の場合、「狙いが遠い場合」「馬に乗っている場合」といった具合に、弓の引き方を多様に説明していました。
このように考えると、弓の引き方に関する理解が深まります。多くの弓道家は、胴づくりで大切なこととお話しすると「背骨が真っすぐになっていること」と説明します。しかし、それだけしか勉強しなかった場合、それ以上難しい内容について本や稽古で理解できなくなります。
胴づくりで「姿勢を真っすぐに」としか理解しないと、射において会に入ったときの「伸び合い」「詰めあい」「やごろ」といった言葉の意味がわからなくなります。文章では言っている内容がわかりますが、それを具体的に実践することができなくなります。
そのため、胴づくりは「的中のために中胴が適している」という安易な解釈はやめましょう。今回の、重賢氏の答えた「胴づくりには様々な場合がある」という考え方は、文献を調査するうえで重要な考え方です。あらゆる状況や主語の対象を変えることで、文献が読めるようになっていきます。
第三条弓構之事
左右中段、単之身。的割四寸之構と号して印西用之。巻き藁間之定法三度見ること。項の髪。袴腰、鉾臥の準、七珍万宝念外のこと。
日置流では弓構えに右段、左段、中段、ひとえの身と四つの弓構えがあり、右段は自分の左斜め前、中段は自分の左真横、左段は自分の左後に弓を構えます。
「ひとえ(単)の身」とは中段の構を左肘を脇につけて構えて、印西先生が、「的割四寸の構」と称して用いられたといいます。
これは弓の幅を一寸(約三センチ)とすれば、横身巾四寸(約十二センチ)として敵より見るとき、弓の幅にて確と我方を見かねて射にくく、我身の楯になるからです。
「巻き藁間の定法三度見る事」とは、身の中心より巻き藁まで弓一丈を定法とします。「三度見ること」とは立って一度、矢番えて一度、弓構えのとき見込、最後まで変えず都合三度に見る意味です。
古伝では立、足踏みするとき一度、矢を番えて一度、構えて一度とします。現在、普段の稽古(的前)のときも、足踏みに一度矢を番えて一度、弓構以後見込んで都合三度見ることが普通となっており、古伝のとおりかもしれません。
「頂の髪」とは「頭持の準(ずもちのかね)」で左眼は目尻、右眼は目頭にて的を見るのであり、往昔はまげに結んでいたため、うなじの髪が二、三本ひきつるとの意味です。
古伝では五、六筋ひきつると言って要は首の筋肉を真っ直ぐに立てて頭持ちすることです。
「袴腰」とは袴の腰板がぴったりと背につくように腰を詰めること、袴腰の準といいます。
「鉄臥の準」とは、弓構のときの弓の伏せ具合をいい、この伏せた度合は終始変わっていないので、的に向かって一尺五寸(約四五、五センチ)前に四寸(約十二センチ)が準となっています。古伝では「矛先伏せたる準」といっています。
「七宝万年念外のこととは」とは引くに当たって、諸種の欲を捨てないといけないことです。
この教えが弓構えの段階で書かれたことが重要であって、弓構えを終わったときはすでに、心の一間中住の心境になりきっていて的以外はなに物もないです。
われも的も、的と自分との空間も一切がひとつとなることを要求していると思ってさしつかえないので、いよいよ動的な行射に入る前、足踏み、胴造、弓構が終わるとき、「七宝万宝念外に有る可し」との古伝は意義が深いです。
三条の疑問点
この項では弓構えでは「構え方」「弓の伏せ方」「袴腰の状態」「欲を捨てた状態」について解説しています。このような文章を読むときに、気をつけなければいけないことが、「先生の意見」が絶対と解釈することです。
まず、古くの文献を観察すると、全ての教えに「決まったもの」が存在しないことがわかります。足踏みの踏み方も、「右足が前に出て有効な場合」「右足が後ろに出て有効な場合」が存在することを説明した文献もあります。さらに、手の内においては、老年に限り、弓が照っていても問題がない場合があります。
すなわち、これらの文章を見てもわかる通り、弓構えには決まった答えは存在しないという解釈が前提です。そのうえで、日置印西派は的の割る位置を定めて「日置印西」の弓構えと称しました。
しかし、。斜面の弓構えは他の流派は微妙に異なります。尾州竹林の場合では、日置流と弓構えの形が少し異なります。ただ、これら形が違うのは「流派で差別化させるための後付け」です。日置印西も尾州竹林も、その源流は日置弾性正次の「日置」から来ています。
したがって、「日置の弓構えは〇〇で▽▽」「尾州竹林の弓構えは◇◇」とあまり形にこだわらないようにしましょう。八十八か条に書かれてある通り、弓構えは「左右中段」と形態はいくつかありますが、「適したもの」は存在しないからです。
第四条引きようの事
五つあり、矢を引く、弓を引く、差別のこと
「引きよう」とは、打ち起こしてより身に引きつけるのに五つの引き様があるという意味です。師伝によれば、
①的の上につけて引きおろす、②的の下から上に引き上げ、③前から後に引きつけ、④後につけて前に寄せる、⑤前上より後下へ引きつけるの五様の引き方です。
最後の⑤の引き方を中を引くといわれており、最上としています。目通り四寸(約12センチ)沖を引くのです。
古伝の解釈としては①頭の上にかぶるように引く②遠く外に回して引く③引き始めに下げて、後に平らに引く、④身に近く引きつけて引く、⑤中を引くとて徐々に近づけつつ、引き分けてくる、この五つの引き方を挙げています。
「矢を引く、弓を引く、差別のこと」とは押してを的につけて、勝手のみに引くのを矢を引くといい、押手にて、すなわち弓にて矢を摺る気持ちで押手張りに、左右に引き分けるように引くのを弓を引くことです。
・第五条矢束のこと
神代の準、大きり三分の一
古伝によれば、矢束の「束」とは神代の項に「束、一束を知らずんば有るべからず」とあり、一握りを「束」と言います。一束を二寸五分(約7、6cm)としました。
矢束は三度に引き込むを定法とし、弓構えで矢束を三つに分け、その一部を押してに、三分の二までに、残りのうち三分の一つを左右に引き分けます。
「三分の二」の位置より、詰め合いまでに残りを左右に引き分けて都合三度、押手に二、勝手に(右手)一の割合で引くべきです。
これにより、吉見順正の射法訓にも載っている「弓手三分の二弓を押し、妻手三分の一弦を引き」と同じ内容になります。
第六条剛弱のこと
剛弱なり、因果所と称うること、また射形にも剛弱あること
弓の形(なり)の名所に上に「柔剛強弱と形傷(なりば)」があるがこれを略して剛弱といい、弓を引くときは剛が手の内にこたえるもので、この剛を押す気分でないと矢は真っすぐに飛びません。
剛を押すと言って上押しを聞かせねばならないのです。九部の力で剛を押し、残る一部の力を離れ時にになおこれに加えて押せば調子よく伸びえます。
射手にも剛弱があり、射形の良い、中る射手を剛、これに反するものを弱といいます。
上押しを効かせる射法は日置独特の射法です。現代の自然体を目指す弓道では、上押しではなく「中押し」を重視させます。
第七条恰好のこと
鉾に相応の矢束、部に合して矢の軽重あり。印西は貫目を以て之を知ること
「恰好」とは弓矢のつり合いを言います。「鉾」とは弓のことで、弓の長さに対しての矢の長さは一定の関係のもとに限られたものです。
弓といえども一種の弾性体であり、戦前において、現浜松工第の福原達三教授が研究された「弓の力学的研究」の中の現実の弓に対する実験報告があります。
弓幹に作用する曲げモーメント(実験結果4)文中、矢束に対する曲げモーメントを測定した結果です。
約2メートル21センチ(七尺三寸)の弓においては約83、3センチ(二尺七寸五分)の矢束までは反発力が矢を引いた長さに比例して増しますが、約83.3センチ(二尺七寸)を過ぎると引いたほど増さないという結果が出ています。
第七条の教えでは2メートル27センチ(七尺五寸)の弓に矢束約90センチ(三尺)、約2メートル21センチ(七尺三寸)に約83,3センチ(二尺七寸五分)、約2メートル15センチに約75.8センチ(二尺五寸)の矢束が相応と言われています。
もし、この割合を失して引いたら、弓の竹切れなどの生じやすいと言われています。あるいは、この割合以下で引くときは矢飛び悪い恐れがあります。
「分に合わせて矢の軽重あり」とは6部の弓に約22、5グラム、七部の弓に約26.3グラムの重さの矢を使うことで、日置流では離れの軽く、鋭いことを修行のため軽い矢を用います。
離よきことのため矢飛び早くするために、いたずらに軽い矢を使えば角見が効かずに中りません。中りを求めれば軽い矢を使われず矢飛びが悪いのです。
「印西は貫目を持ってこれを知ること」とは弓に適した法を印西先生が定めたので、その法とは平素射慣れた弓を矢束だけ錘りを定めておき、矢束を10等分して、その一つが上がるか下がるかで、矢の目方を一定の目安で増減させます。
つまるところ、たくさん引けば、矢飛びが良いかというとそういう話ではないことが分かります。まして、弓が強ければ矢飛びが早いと、そういう話でもないです。
矢飛びを増減させるには離れを鋭くさせるには、たくさん引く意識と「方向性」が大切になってきます。これは、六部の弓を引くときにも同じで、押し開く意識と、会のときに「どう伸びるか」という感覚を自分でつかむ必要があります。
日置流の射法では「会の時の拳の位置より一つ拳分よったところを押すように」と表現しているし、小笠原では「肩と胸が詰まるように」と説明しています。
私なりのすべてを読んで、意識していることは会で押し開くは「真横に開く」と考えています。会に入ると、肘先が下に落ちる人が多く、肘が下に落ちると、離れのときに、離れの方向と押し開く方向が一致しません。
この意識と、方向性が各人の矢束を決めてくれます。引き方を知るのではなく、理解するためには、たくさん引くこと+αを行う必要がでてきます。
第9条つめの事
勝手にあり、矢束縮むること、一寸の開き五部の詰、音輪を用いること
「つめのこと」とはゆがけを自然に内へ捻ることを射手詞(射手言葉)でツメというので勝手にありと記した。詰め所が悪いと矢枕が落ちます。
「矢束縮むること」は矢の差がルとき、手首折れるとき矢束を詰めてひかせる。このようなときに次の「一寸の開き、五部の詰」の心得が必要です。
すなわち弓を角見にて一寸(約三センチ)強く、押し開くとき、肘を五部強く詰めて離せばわずか詰めた矢尺は矢飛びに影響しません。
この一寸(約三センチ)の開きの角見の働きは師の目にも見えないため、昔は弦音で判断していました。そこで弦に鉛をしかけて音輪をしかけて判断の良しあしを決めていました。
第14条、急雨の事
勝手にあり、切り癖弱気に用ゆ、一文字かけ金のこと
「急雨(きゅうう)のこと」とは、日置流の離れにして軽く、鋭い離れを例えたもので過ぎて後にと思わず、ああよき離れであった、感ずるごときを言います。求めて放ってはいけないという意味です。
「剪癖、離れ弱き」とは文字とおりの意味で、剪癖とは放つに及んで満ちて離れず、力を持って引き切る癖(相当年数修行した射手もこの癖を持つものが多い、注意すべき)、つけ離れ、弛み、弱き離れなど皆勝手の病であります。
これを治するのも直接は勝手(かって)によるゆえ「勝手にあり」と前置きしたのです。勝手肘尻に力を入れ、手先に張った糸を緩めることなく、肘先で後のものを付くごとく放つを修行すると以上の病癖は治るものです。
第15条、朝嵐のこと
勝手にあり、肘よりゆがけの法に癖あるを用ゆ、日風呂空の指に口伝。
「勝手にあり」とは、取り懸けに関する事柄であるのかくいったので、「肘よりゆがけの方に癖あるを用ゆ」とは文字通りの意味、「火風空の指」とは中指、人差し指、親指のことで、取り懸け様の口伝であります。
指先のしがむもの、離れに悪い癖のあるもの、射流しの際などに用いることであります。その方法は空(親指)はそらし、風(中指)は火(人差し)に添えるのみとし、火の指は軽く親指を押すのです。
しかし、これは実際は軽すぎて心にかかり、返って指先に力が入りやすいもので、未熟な射手が試みることは早気の生じやすい危険があります。
初心者で離れで求めるのはなく、引き分けで大きく、押し開くことを考えて稽古を行うことが良いでしょう。
第16条手の内十文字のこと
矢を屈たるところ、左の腕、掛、腰、引渡し、この五つ五十なり、又十五十口伝深し掌と号くる事口伝あり。
この文章の説明のまとめ
射を行う際に、形の上で十文字(直角をなすこと)をなす箇所を五つ説明していることがわかります。掌は的中、諸種の病癖の元ともなるので、五つの代表として手の内の十文字を加えて個条の名としました。
「五つ」の十文字とは矢を番えて弓と矢、取懸をしたとき左の上膊と弦、「掛」とは弽の拇指が取り懸けたとき弦と十文字、「腰」とは胴と両腰骨が十文字、「引き渡し」とは、詰め合い以後矢は首と十文字となります。
この五つの十文字が完全であり、会の働き正しければ残身は正しく、左右の手は同じ高さ離れて異同なく、胴と十文字をなします。
これが十文字を積み重ねて離れた後の十文字であるとの意で十五十、すなわち十文字の後の十文字という意味です。
弓道教本では五つの十文字を「五重十文字」と呼んでいます。この言葉の内容はこの日置流目録の中にも記されています。そして、その五重十文字を形成すれば離れた後の残身も自然と十文字となると説明しています。
疑問点
五十五口伝深しと記しています。この口伝深しという内容は、「指のそろえ方は地方、流派によって」数々あるとという解釈になると考えられます。事実、昔の弓道の書籍においての掌の説明は数多く記されています。
後、弓道講座に、掌は的中、射の癖の元となると説明しています。他の書籍(尾州竹林の書籍)となると、病癖に関わる箇所とは記していないことがわかります。さらに、梅地氏は「掌」に的中と因果関係はないとも説明しています。
弓道教本二巻の神永範士も射において、胴体の重心移動を少なくするには、引き分けにより、「矢の線」と「両肩の線」を近づけることを説明しています。
さらに、「左の腕」「掛」「腰」「引き渡し」の言葉が正しければ、弓道教本一巻の五十重文字と同様の内容になります。しかし、教本における五十重文字は「適切な弓の引き方になるか」は疑問が数多く残っています。
第17条紅葉重ねのこと
掌口伝、手を不撃、弓返り鉾なり能く、弦強くなる、会に達するときは直中胴達決定なり。飛井雅章おきの八雲御さのこと。
文章の説明
「掌口伝」は手の内の作り方を口伝によれということで次のごとく作ります。親指と人差し指の間の皮を弓にあて軽くこきあげます。このとき上述の二指の股の中心を前竹の右七分、左三分のところに当てます。
そうして掌を弓と十文字にして天文筋を外竹左角に当て、小指親指に近づけて巻き付け、無名指(薬指)を小指にそろえて巻き、親指と無名指(薬指)の間に無理に外竹の側より中指を差し込みます。
そうすれば掌はしまりひねりやすく弓の反発力を最大限に生かし、矢飛びよく、弓返り強く、把は低くとも手を打たず、把高き弓を射ても弦の納まりよく、鉾の位置をよく止まります。
矢押しがよくなることを射手詞(いてことば)で「弦が強くなる」と言います。「八雲御さ中」とは人の手の美しいのを楓(かえで)に例えられた文があるので、掌を紅葉重ねと名づけられました。
この掌がよくでき、技に達するときは中りはもちろん貫徹力も十分備わります。
疑問点
まず、「紅葉重ね」を手の内に説明しているのは、浦上範士の書籍のみです。この説明が正しいのかが根拠がわかりません。現に同じ日置流の(日置尾州竹林流)の紅葉重ねは残身でこの言葉をしるされています。さらに、手の内で弓返りがよく、弦強くなると記しています。
弦音が向上するかは、手の内ではなく、右肘の位置によって、最大限に矢束をとった会の状態によって体現されると他の書では説明されます。
鉾なり良くとも記されており、会における「弓の上部」の状態を指しています。しかし、上部の押す場所以上に的中にかくぁる要素が存在するため、受け入れて良いものか詳しくはわからないでいます。
第18条角見の事
真、草、行あり、弦道あけん為なり。
「角見」とは手の内を調えるとき、左の親指の付け根と弓の前竹の角(往昔は前武の幅6分)を互いに見合わすようにするのでこの名があります。
「真、草、行」の三字は角見の働きを三つに分け、「真」は弓の角を押しひらく、「草」は親指と人差し指の股と弓の関係、「行」は小指、無名指の締まりを言っています。
みな弦道を明けて的中をよくするためであるとの意味です。
第20条弦三所に納まると事
手先の清濁は位の空虚にして師匠の目にも及ばぬ程の濁は必ず弦に顕はるるなり、遠矢四町に達せず、堂の少しかかるは濁有故也。弦袮、弦音、弦拍子三つを毅音と云ふ。
「弦三所に納まること」とは離れて弦がもとに納まるとき、上、下、中と納まるのをよしとし、一度に納まるのはよくありません。この弦の収まり具合によって弦音(つるね)に相違がでてきます。
「手先の清濁うんぬん」とは押手の角見の働きの良否は、すなわち師の目にも見えぬ程度のわずかの角見の鈍さは弦音に現われ、弦の納まり具合で弦音がつやのある音か、汚いべしゃっと音になるかが決まります。
遠矢が四町に達していた射手や、三十三間を射て堂の通っていた射手が四、五間の差で四町に達せず、縁にかかるときは、弦音に濁りがあるためで、角見(つのみ)が効かないのが原因です。
小的を狙うとき、矢が的の周りに散って中らないときも射に濁りがあるときです。
「弦ね、弦おと、弦拍子の三つをうんぬん」とは初心者の角見の効かないとき、弦が上部、下部が同時に納まり、音高くなります。くこれを弦音(つるね)といいます。
中位の射手の音高きも音が納まり澄んだ感じになります。これを「つるおと」といいます。上級者になると澄んだ音で高くなく、弦音はこれを弦拍子といいます。
一説によると、弓返りして納まった後に出る音を弦拍子というときもありますが、これはきわめてかすかな音で静かな場所で引いても聞こえないことがほとんです。
本人か近くの者しか聞こえず、よほど角見が効き、残身の弓の納まりよく、手の内がしまらぬと鳴らないものと言われています。
現代弓道ではこの弦道と弦音に関する重要性を欠いているのが現状です。上級者でも弦道が一定にならず、弦音も澄まず(音が高くない人はいますが)、弓の関板付近に当たった音がなっている者が多いです。
日置流ではこの弦音が高くなく、澄んだ=角見が効き、胴を直なる合理的な射ができていると説明していますが、弦音と矢飛びの関係も説明されています。
弓の関板に弦が当たって弓返ると矢飛びの勢い、早さをなくします。単純な話ですが、これは弓師さん、弓の職人ならこの話を知っています。弦音は弓にあたらずに出る音が理に適っています。
音としては擬音で例えると弓の関板に弦が当たったときの音は高く「べしゃあぁーん」という音がなります。しかし、これが当たらず、角見が効いた弦音だと「じゃいん」と短く、音高くなく、聞いてて納まりある音に聞こえます。
第21条矢通間と云事
四つ有之事、押手勝手離よし、離濁る、勝手能く押手悪しく、押手勝手放れ悪しく、右四つの矢通間のことを云ふ三拍子備はる射手は一間より二間なり各口伝
「矢通り」とは矢勢のことをいい、押手、勝手の善悪によりいろいろと変わり、矢色によって知ることができます。
「押手勝手離れよし」とは、この場合矢行き真っ直ぐに飛び、矢の場合は四丁のうち、二丁は上り羽、二丁は下り羽で距離も延びます。「離れ濁る」とは勝手の具合悪いときで矢は上下に振れます。
「勝手能く押手悪しく」は、離れよく押手効かぬときで矢は左右に振れます。「押手勝手離悪しく」は押してが効かず、勝手または離れ悪いときは矢は根と筈と交互に描いて飛びます。
この四つを言っています。押手強く、勝手鋭く、離れそろう三拍子の備わった射手は矢行強いため、近くより、ちょっと距離を置いた物がよく貫けるようになります。
具体的には矢自体の振動の取れる二間より三間、三間より四間と七間くらいまでは離れるほど物はよく貫けます。
第22条骨合筋道の事
初学より之を用いる時は力味なし強みを射ると云う事専一なり、強弓を引き弱弓にして力越さぬなり、又先達離は押手勝手共に之を禁ずべし
初心者に教えるときは、十文字の準に合わせて全身の力が偏ることなきように素直に引かせるのがよく、この全身の状態が十文字の準に合い、釣り合った状態を「骨合筋道(すじみち)」と言います。
各関節が正しく力の働きが最も効率よい状態にあることでこれを他流では「骨法正しく」働いていると言います。
もしも、射手がこの理論を教わる場合、指導者がその人の体格を考慮し、準に合わせて指導するならば、力が一方に偏ることなく、力いっぱい弓が引けます。「強みを射る」とはこのことの意味です。
強弓を引くにも、準正しく修行するも射そこなうことはありません。応分の力とはその時々の最小限の力を使うことで、離れの前の、延び合いに対する準備とともに思えるもので大切なことです。
「また先達離は押手勝手ともにこれを禁ずべし」とは、離は総体にて、どこということなく離れるべきであるのに、押手、または勝手より離を作ったり、誘ったりすることは、早気の原因になります。
骨法の話は「尾州竹林」「本多流」「射学正宗」にも記載されている射の考えです。まさに強弓を引くときに必要な考えであり、各人のそれぞれの「人の数だけある理にかなった射」を見つける方法です。
骨法の話は射学正宗では肩甲骨、肩関節上部など骨の部位を強調した教えです。射学正宗では弓を強く押すために、左肘裏の皿上部をやや立てるように押していくと説明しています。
他に骨法には、各関節に焦点を当てた説明もなされています。たとえば、日置流の取り懸けの説明の懸口十文字とは、右手首と弦の間に角度を作らないことを意味しています。
押手の押す形としての「中押し」というのも、左手首と弓の間で角度を作らないことを意味しています。手首が内や外に曲がっていることは「骨法が納まっていない」ということになります。
肘の納まり、会のときの手の内の形、これらも骨法骨相の話で出てきます。人それぞれ関節の長さや大きさ、位置は微妙に違いますが、「納まるところ、納まる感覚」は人それぞれ持っています。
なので、指導者は初学者に引き分けを教えるときは形ではなく、目いっぱい引かせる意識づけにて自ら「引き満ちた状態」を体感させることが役目になります。
形を覚えさせるのは本当に初期の段階で慣れてきたら各人の骨法に合わせた引く指導や考えを持って弓を引くことが大切になってきます。
第25条
不引矢束の事数々駅あり、矢通り間強く先達を治するなり、係迦を心得て常に勤む、この業の大事は外れて気の別れざるように射発すべきなり、早気つくならば、当分この習を止めて別つの教えをもって早気を治すべきなり
「不引矢束」とは自分の矢束をいっぱいに引き取り、気を込めて、力をゆるみなく押引きするうち、自分の判らぬまま離れてのちはじめて「ア、離れた」と思われるような無理のない離です。
このように、自然と発射されるのを、「引かぬ矢束の理」というので、弓人至高の技です。
「数々益あり、矢通り先達離れを治するなり」とは延び合いの極限、やごろに達して、矢勢殺(そ)がれず最も強く、左右完全にそろって発射されるために押手勝手が先立ちことです。
「係」とは勝手の掛け具合を始めとして、勝手の一切のこと、「迦」は引かぬ矢束で業に気を加えて自然に発する詰め合いをいい、この二つの事柄を常に修練せよという意味です。
「早気つくならば云々」とは、早気のものは引かぬ矢束にいかに理あるともこれを行えばますます早くなるので、引く矢束にて当分修行し、早気治ってより、また、引かぬ矢束を修行すればよいです。
弓道教本第二巻にある、教歌で
引く矢束引かぬ矢束にただ矢束放つ矢束にはなさるるかな
(琴玉歌)
とあり、引く矢束は意識して勝手に引くため。自分で放つことになり、引かぬ八束こそ自然に満ちて離れるので、離ともいうべきです。
ただ矢束とはただ一定の矢束を保つのみで会の働きがなく、やがて弓の力で矢を引き出されるように放れるので、放さるるといっているのです。
第28条矢の和可連の事
弦の別れ弓のわかれ四寸の別共(わかれ)号(なづ)く。この別を号くるに差別あり、また矢の軽重によりて別のせんさくあり、手を打つ射手の別れあり、毅音を知ること肝要なり。
これは矢が弦と離れる時期、タイミングを説明しています。「弦の別れ」とは、ちょうど張顔の弦の位置ですなわち把の高さで弦と矢が分かれることをいい、比較的初心者か手の内の効かない射手の場合であります。
「弓のわかれ」「四寸の別れ」とも言います。握り皮と弦が四寸くらいまで接近したときに矢が分かれることをいい、上功の射手すなわち角見の効くときの離です。
矢は筈で弦を引っ張り、把の高さより内に、手の内に接近して分かれてきます。これは十分に弓の力を矢が受け取り、しかも速く飛ぶので、弓の復元より早く把の高さの位置に通過しているためです。
高速度フィルム(千コマ毎秒)による測定実験では、この「四寸の別れ」の瞬間をカメラで計って確認された話があります。
この実験ではと弦と矢が離れるタイミングは把の高さより内に来ているとわかったのです。把の高さより内で筈は上下弭と直線的に結ばれた形、すなわち弦を筈が弦持(つるもち)で引っ張った形のところで離れていることがわかりました。
この話は日置流射法を学んだ範士十段、教本第二巻に載っている射手浦上栄範士も昭和初期実験を計画していました。旧海軍兵学校関係者の協力を得、一秒間120回転で離れの瞬間を正面、右側方で撮影した資料があります。
その右側方の撮影した写真で弦と矢が分離する寸前の写真では、確かに矢と弦が把より内側についている写真がありました。


矢が軽すぎる場合は矢の加速が急に過ぎて弦より早く離れ、弓の力を受けることが少なく、初速は速いが速度の維持が少なく、俗にいう空飛(そらとび)をして的中も悪く、力もありません。
力は運動させられる物質の質量と加速度をかけた値ですがその質量は弓と弦と矢の質量に関係して、この三者の均衡が取れず、矢がとくに比較的軽いときは「空飛び」が起こるのではないかと考えられます。
矢が重いときは以上の理からちょうど角見が早く効いたように弦が押して行き、弓の力が十分に伝わると考えられます。
「手を打つ射手云々」とは、角見先だち、勝手そろわず、重く放たれたとき、角見効かず手首でゆるみ、弓のひねり効かぬときなど、弦は外に回らず、弓の中に向けて戻ります。
よって、弦は左肘、または手首の辺で矢と分かれる場合で手首脈所、親指根の辺で打つのです。これも高速度写真の実験で証明されています。
「毅音(きね)を知ること肝要なり」とは、矢と弦の分かれは目に見えないので弦音によって判断するしか方法はなく、「弦の別れ」は弦音高くしかも音が割れます。「弓の別れ」とは弦音短く澄むものです。
音を用いれば区別がしやすくなります。