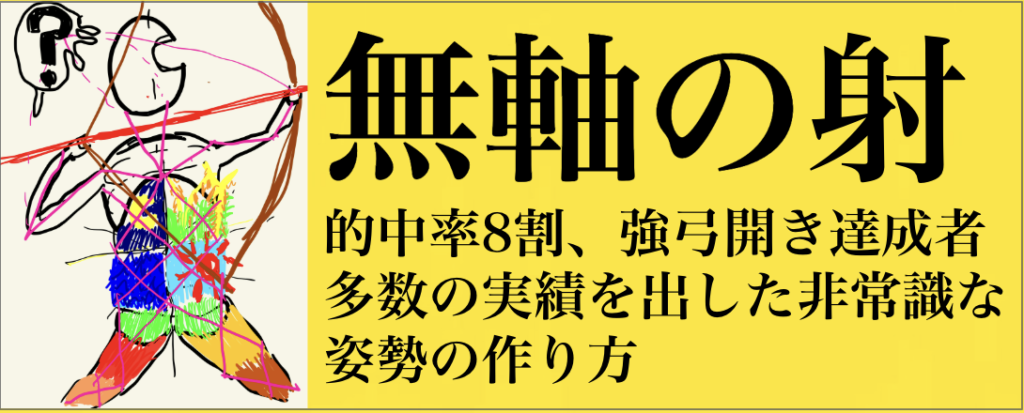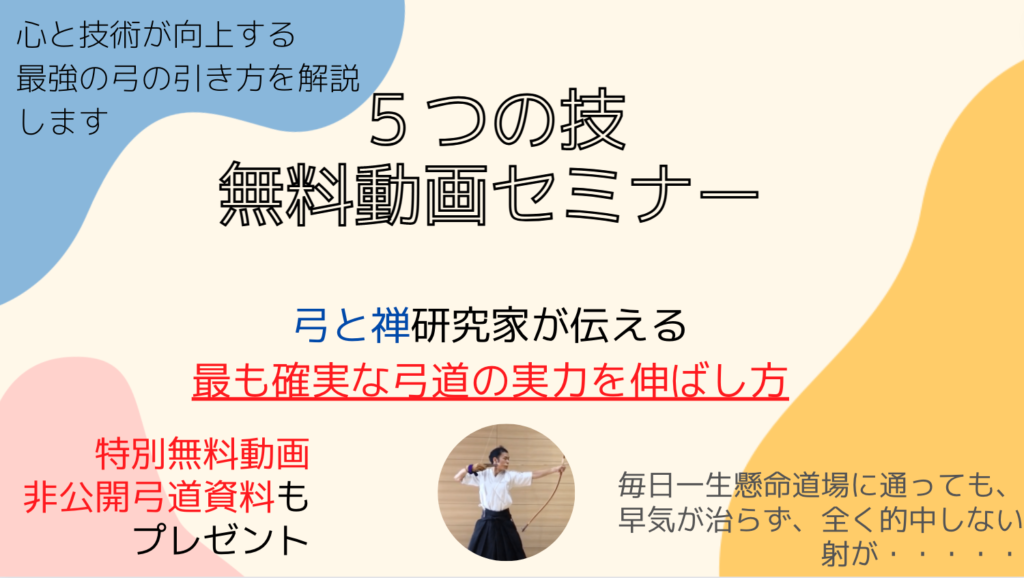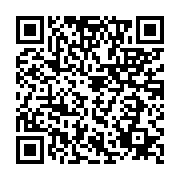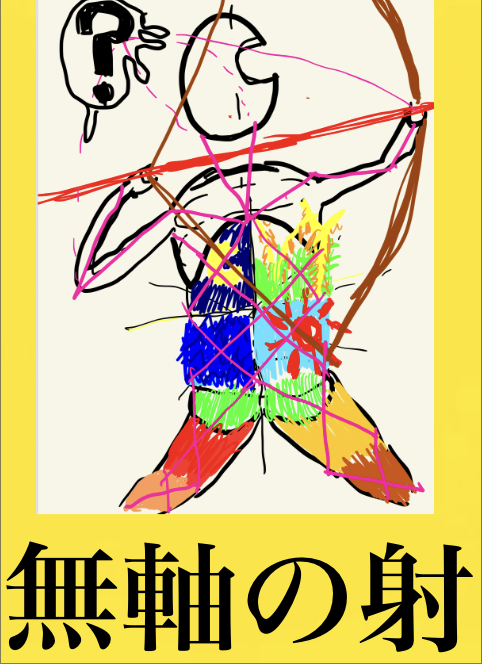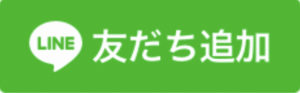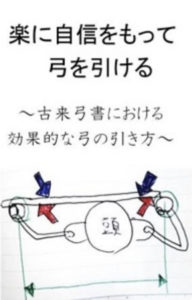今回は弓構の作り方について解説していきます。
1. 中るかどうかは弓構で決まる
当サイトでは、的中や強弓引きを実現するために大切なこととして
中るかどうかは弓構えで決まる
と解説しています。
まず、射の成否を決めるのは「打ち起こし」の段階 であることが多くの文献に記されています。
・起こり悪ければ、終始にしがたし(本多利実「本多流弓術書」)
・打ち起しの正否が射の正否を決める(梅路見鸞「心月射儀」)
特に強い弓を引く場合、打ち起しで姿勢が崩れると弓の反発に押されてしまい、身体にかかる負担が増してしまいます。
そのため、打ち起こしの段階で正しい弓構えを作ることが、弓道の上達には不可欠 です。
つまり、正しい姿勢を作らないと、正しい打起に移ることができないと解釈できます。
では、正しい姿勢と腕の動かし方を解説します。具体的には
脚で自然に腕を体に引きつける
この動かし方だけ覚えてください。
弓構えで注意しないといけない部位は、胸でもなく腕でもありません。「脚」です。
さらに、具体的な体の動きを覚えてほしいのは二つだけです
脚を後ろに引けば、腕は自然に体に寄せられる
胸を開いていれば、上腕は外旋・前腕は内旋する
と覚えてください。この2つを覚えれば、自然な弓構えは完了です。
そして、自然に脚が開き、胸が開かれる姿勢の作り方を解説します。
1足踏みで両脚を閉じて、中心に寄せるように意識します。
この動きにより内転筋が自然に縮みます
2力を抜いてください。両脚が自然に開かれます。
内転筋が伸びて、自然に両足が開きたくなります
3脚の筋肉を後ろに引くようにします
内転筋は、太ももを内向きに向ける骨です。
4背骨が自然と立ち上がります。
ここまで行うと、自然に両胸の筋肉が左右に開かれます。そして、両腕が自然に体に寄せられると思います。
これが、弓構です。
ここで、多くの人が、弓構を両腕を体の前に差し出すように動かし、両腕で円形に囲い、弓と矢を持つようにすると思います。
そうではありません。前に差し出すのではなく、両腕を近くに寄せる過程で両腕を円形に囲むことが大切です。こうすることで、
この際に腕が体に近づきます。これが弓構です。弓構とは、弓を持って構えることが弓構えではありません。自分の体の自然な動きの中に弓を取り込むことです。
自分の自然な腕な腕の動きの中に弓を取り込み、次のうち起し動作をしやすいようにします。
🔳手首を捻ろうと意識しない方が捻られる
よく、弓道の先生は「右手首を捻りましょう」と指導をされることがあります。これは、右手首
🔳円相は両腕が広がることを指す